「税未納の外国人在留延長認めず」の衝撃
本日の日経新聞1面に「税未納の外国人在留延長認めず」という記事が掲載されていました。出入国在留管理庁と厚生労働省が、在留外国人の税や保険料の滞納状況を共有する仕組みを整えるという内容で、情報共有にはデジタル庁が構築する省庁間の情報連携システムが活用されるとのことです。
この記事を読んで、「ああ、やっぱり行政のデジタル化は遅れているな」と、どこか諦めにも似た感想を持ちました。
行政内部のシステムは「紙文化」から抜け出せず
行政のデジタル化は、本当に遅れています。
よく「ICT機器に慣れていない高齢者への配慮から、紙による対応も残している」と言われますが、これは住民対応の話であり、行政内部の業務システムとは別の話です。
このような状況は、伊那市でも同様です。
笑われるかもしれませんが、メールで送られてきた文書も、プリントアウトして回覧文書とし、担当者から必要に応じて市長までハンコが押されます。メールの意味がありません。しかも多くの文書は、いまだに紙で回覧されているのが実情です。
行政は文書の塊のような組織です。一日でも不在にすると、机の上は文書を挟んだ決裁板の山になります。
昭和のような手作業が今も続く
さらに、これは笑いごとではありませんが、非正規の「会計年度任用職員」は、日々の出勤について紙の出勤簿に毎日押印し、出勤日数や欠勤・超勤・有給などを自ら記入します。月末にはそれを庶務担当が手作業で集計しています。まるで昭和の時代のような作業です。
行政は、自らの業務を効率化することで人員に余裕を生み、その分を削減したり、市民サービスの充実に振り向けたりするべきです。「システム開発には多額の費用がかかる」と言い訳されることもありますが、それは将来の市民サービスの向上と事務効率化のための「投資」と捉えるべきです。
自らの業務を省みる姿勢と、それを実行する取り組みに期待したいところです。
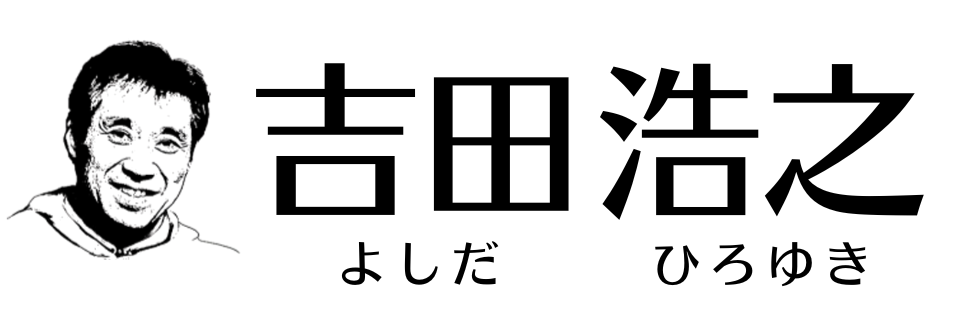









コメント