ハンナ・アーレントと全体主義の研究
このブログをお読みの皆さんは、ハンナ・アーレントという政治哲学者をご存知でしょうか。
ナチスドイツをはじめ全体主義について研究され、『全体主義の起源』という著書が有名です。
その中で、全体主義の流れや定義、ナチスドイツについての考察が記されています。その一つに、なぜユダヤ人の大量虐殺が可能だったのかという疑問への答えがあります。アーレントは、それを「職務に忠実な役人が、自分の善悪の判断を入れず、淡々と職務をこなしていたから」と説明しました。
彼女が注目したのは、収容所の移送責任者であるルドルフ・アイヒマンという役人です。彼はユダヤ人抹殺に使命感を持っていたのではなく、与えられた仕事(収容所への移送)をただ淡々とこなす役人に過ぎなかったとされています。
イエスマンの危険性
つまり、問題なのは「自分の頭で善悪を判断せず、与えられた職務を忠実にこなす」という姿勢にあると言えます。
公務員の場合、この態度が時として市民に大きな災いをもたらすことがあります。上からの命令や指示を忠実にこなすことは大切ですが、それだけでは誤った施策につながりかねないのです。
言われたことを何も考えずに遂行するだけのイエスマンであってはなりません。時には立ち止まって考え、「これは間違っている」と思えば、上に意見することも大事な職務の一つです。
上に立つ者の役割と度量
何よりも大切なのは、そうした意見を受け入れられる上司側の度量や余裕です。上に立つ者の判断が常に正しいわけではなく、むしろ誤っていることの方が多い場合もあるかもしれません。だからこそ、様々な意見に耳を傾け、情報を集めた上で判断することが、上に立つ者の本来の役割なのです。
もちろん、下から意見されるのは気持ちのいいことではないでしょう。しかし、それを避ければ、組織は誤った方向に進みかねません。特に公的機関においては、誤った判断が企業以上に、市民全体に影響を及ぼします。
安易な方法に頼るべき時代ではありません。大変であっても、様々な声を聞き取り、それを判断に活かすことが重要な仕事だと言えるでしょう。
#伊那市 #吉田浩之 #ハンナ・アーレント
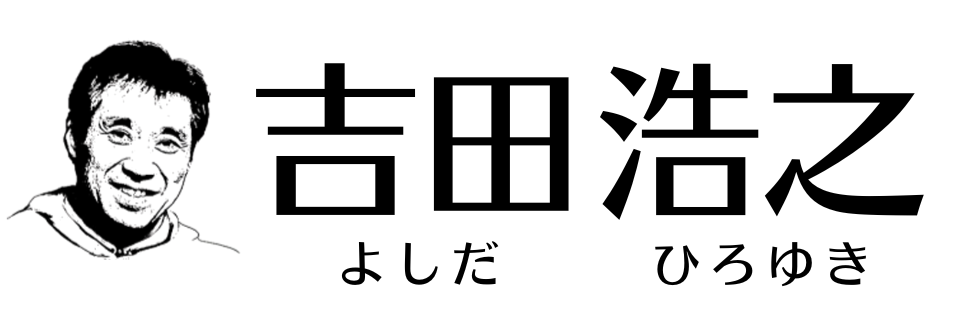









コメント