ガソリン減税とは何か
今日のニュースで、ガソリン減税の年内実施について与野党で合意がなされたと報道されていました。
そもそもガソリン減税とは何でしょうか。
ガソリンの価格には本体価格に加え、石油製品関税、石油石炭税、ガソリン税、地球温暖化のための税(これは環境税とも言います)、そして消費税の5つの税金が課せられています。
このうちガソリン税には、本来の税額のほかに上乗せされた「暫定分」があり、この2つを総称してガソリン税と呼んでいます。その暫定分(25.1円)のことを「ガソリンの暫定税率」と言い、この部分を廃止することをガソリン減税と呼んでいるのです。
また、消費税はガソリン税や環境税を含んだガソリン価格に対しても10%課税しており、税金に対してさらに税金をかけている「二重課税」状態が問題視されています。
減税の効果とその是非
さて、このガソリン減税ですが、暫定分25.1円が軽減されれば、全国平均で見ると1リットル平均174円(うち10円は現在の価格補助)であるガソリンが、補助金を廃止し暫定税率も撤廃すれば159円になる計算です。
確かに25円も安くなれば、消費者にとってはありがたい話です。
しかし、本当に安くしてよいのか、慎重に考える必要があります。
安くなれば消費者は恩恵を受けますが、その分消費量も増加し、脱炭素を目指す国の方針とは矛盾することにつながります。国立環境研究所の試算によれば、2030年には二酸化炭素の排出量が7.3%増えるとされています。
国の方針と矛盾してでも、国民が恩恵を受けられるようにすべきなのでしょうか。
ドルベースで各国のガソリン価格を比較すると、日本は決して高いわけではありません。IEA(国際エネルギー機関)の調査によれば、G7の中ではアメリカ、カナダに次いで3番目に安い水準です。
景気と政策のバランスを見極めるべき
インフレの中で価格を下げることは、消費を加速させることにつながり、過熱気味の景気をさらに押し上げることになります。これは本来の経済政策に逆行し、景気の過熱化を助長する可能性があります。
「安ければいい」「もっと消費すべき」という考えでは、有効な物価高対策を行っても、その効果は限られます。
ましてや給付金の支給や消費税減税などは、景気の過熱を一層促進することになります。
私たちは本当に何を求め、どうすべきなのか──一人ひとりがしっかりと考える必要があるのではないでしょうか。
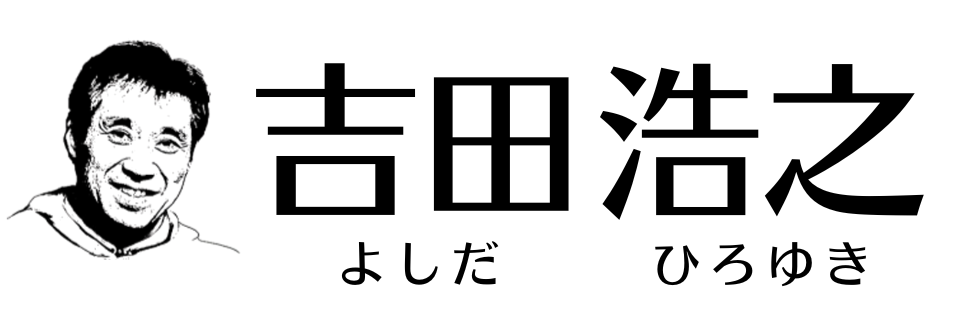









コメント