実証実験の経緯と期待
本日の日経新聞に、伊那市を会場に無人ヘリコプター飛行の実証実験が行われ、途中、予期せぬ出力低下により安全確保のため荷物を途中で切り離したとの記事がありました。これは、川崎重工業が取り組んでいる「Vトール」といわれる大型ドローンで、日経の記事にもあるとおり200キロの荷物を積載できる、いわば「空飛ぶトラック」です。そうした無人の大型輸送機が実際に運航できれば、山岳地帯や防災時の輸送、あるいは送電網の保守での活用が見込まれることから、各方面から期待が大きい事業であると言えます。
伊那市の関わり方に対する懸念
ここまでは通常の企業の取り組みとして話題に挙げられる内容ですが、この事業には伊那市が大きく関わっています。場所の提供だけでなく、事業の資金面でも国の交付金や伊那市の職員が関わるなど市税も投入されているわけです。こうした事業は大きなプロジェクトであり、試行錯誤が多く、成功までには長い道のりがあります。1年や2年で完成して実運用に至るとは考えにくく、だからこそ企業は真剣に取り組む必要があります。川崎重工業が取り組んでいないというわけではありませんが、国などの交付金で事業を行うのであれば責任の所在が不明確になりがちで、結果として社会実装に至らずに終わってしまう可能性も考えられます。したがって、行政が民間企業の開発に深く関与することは望ましくない面があります。
軍事利用の可能性と行政の立場
もう一点、行政が関わる際に慎重であるべき理由は、日経新聞によればこの「空飛ぶトラック」は可搬重量や航続距離の大きさから軍事用途も想定され得る開発だという点です。国防のために市町村が場所提供や支援を行うこと自体は必ずしも問題ではありません。しかし、機材の開発そのものに自治体が関わることは意味合いが異なり、より慎重な判断が求められるでしょう。
行政の役割と優先順位
最先端技術の開発はどの分野でも進めていくべきですが、地方自治体が積極的に関わることが開発を早めるとは一概に言えません。民間で開発すべき事業は民間が主体的に行うべきであり、行政が音頭を取るのは好ましいことではありません。むしろ行政は市民生活に密着した事業に力を注ぐべきだと考えます。
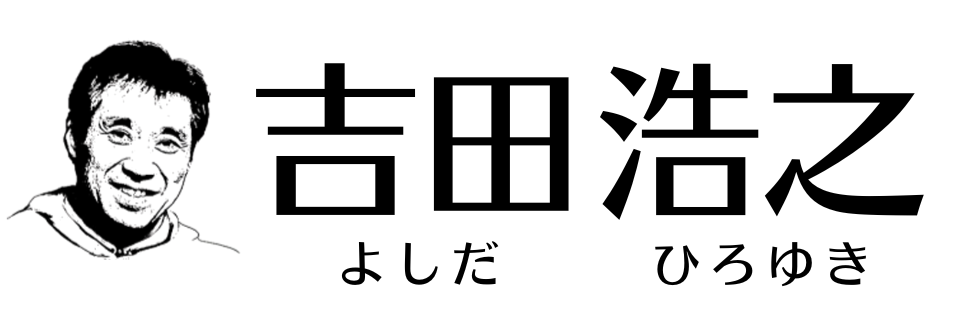









コメント