日本のエネルギー政策の現実
日本のエネルギー政策では、2040年(令和24年)ごろに、原発比率を20%、再生可能エネルギーを40〜50%にするとしています。しかし、洋上風力発電が予定通り進まず、この目標は、かなり厳しいものと言わざるを得ません。
伊那市の「地産地消」エネルギー構想の課題
伊那市では、エネルギーの地産地消と称して、市内で使う電気を市内で賄うとしています。これは、市内での水力、太陽光、バイオマスといった再生可能エネルギーで、家庭電力を賄うという意味だと思われます。
しかし、市内には上場企業もあり、すべての電力を再生可能エネルギーで賄うことは不可能と言えます。
電力需要の増加と再生可能エネルギーの限界
さらに、CO₂排出抑制のために電気自動車の推進を図る一方で、業務の効率化を目的としたAIブームが進んでいます。そのための高性能半導体は、従来よりも10倍の電力を必要としますし、データセンターも大量の電力を常時必要とします。
また、各家庭においても、高齢化とともに火事への心配から、ガスや灯油を使う生活から電気中心の生活へと移行する傾向が増えています。
こうした状況にあっては、再生可能エネルギーで賄うことは、あまりにも現実的でないと言わざるを得ません。
バイオマス発電を推し進めるにしても、山林の伐採には限界があり、伐採にかかる経費では採算も取れないでしょう。
また、太陽光発電で賄うならば、市内全てに太陽光パネルを敷き詰めなければならないほどであり、いずれにしても限界があります。
現実に即したエネルギー政策の必要性
日本においても伊那市においても、エネルギー政策は将来にわたって実際に必要とする電力と、提供できる電力を分析したうえで、絵空事とならない政策を掲げなければなりません。
伊那市ではカーボンニュートラルを掲げていますが、そのために市民に生活の不便さをどこまで求めるのかを十分に議論せず、CO₂削減を錦の御旗にしていては、本当の意味での削減はできないでしょう。
再生可能エネルギーでの地産地消を実現するには、江戸時代とは言わないまでも、70〜80年前のような生活に戻らなければ難しいのです。
社会が電気中心の生活になってきている以上、新たな電力源や原発についても、前向きに考えていく必要があると言えます。
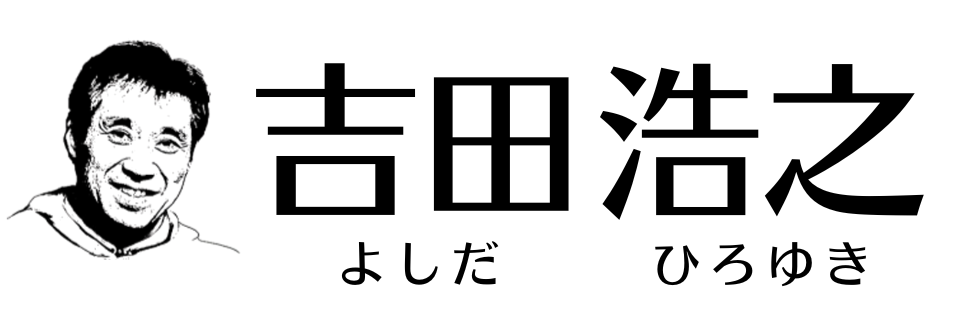









コメント