晋山式とは何か
これをお読みの皆さんは、晋山式という行事を御存知でしょうか。
ウィキペディアによると「晋山式(しんさんしき、しんざんしき)とは、寺院に新たに住職任命(新命)を受けた僧侶が、住職として入寺(晋山)する儀式のこと」とあります。多くの場合、僧侶として一生に一度限りの行事といえます。
こうした寺院での行事は、型にはまり、すべてがその型に沿って行われる、肩苦しいものでもあります。そういったことから、檀家というのは「お金はかかるし、時間も取られる厄介なもの」と考える方もいます。
このような傾向が現代社会では当たり前になり、結果として寺院、つまり仏教(宗教)を遠ざけたり、拒絶したりする人が増えてきています。
宗教の喪失がもたらす社会の不安
今日の日経新聞に、歴史人口学者エマニュエル・トッド氏のインタビュー記事が掲載されていました。
「社会の常識・良識を壊す保守ポピュリズムが世界を覆っていて、その最たる例がトランプ大統領を再選させた米国であり、その先には暴力的衰退を迎える可能性がある」と氏は予言しています。
さらに、「人々に勇気や名誉、真実の尊重などの価値観を植え付け、国や社会を形づくり集団行動を可能にする上で、宗教の喪失は大きく影響し、社会がまとまりを失い、人々の知性も低下させた」と述べています。
現代社会は様々な情報にあふれ、何が正しく、何が間違っているかの判断が非常に難しくなってきています。そうした社会においてこそ、宗教の果たす役割は非常に重要であるはずなのに、その宗教を負担感や煩わしさを理由に遠ざけ、己の経験則だけを基準に諸事を判断していくことは、複雑化する社会において非常に危ういことです。
いつそれが負の力により、かつて日本が経験した悲惨な社会へと進みかねない状況にあるとも言えます。
宗教を「人の規範」として見つめ直す
己の目先の損得だけで宗教を論じるのではなく、数十年後の地域社会や家族のあり方を思い描きながら、人としての規範として宗教に関わることは、これからの時代にますます必要なことではないでしょうか。
朝刊を読み、菩提寺の晋山式に参列しながら、そんなことを考えた一日でした。
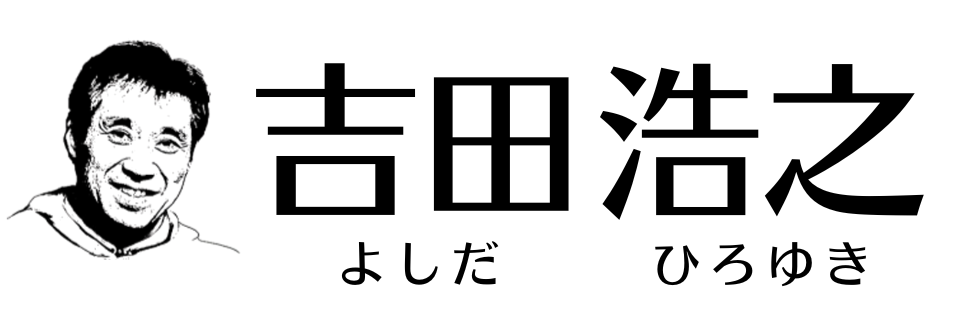









コメント