貧困率が示す日本の現状
貧困は格差社会が言われるようになってから、益々顕著になってきているようです。
貧困率で比べると、欧米よりもその格差は大きくなっています。つまり日本は貧困の割合が大きいということになります。
この貧困率ですが、相対的貧困率というもので、所得が集団の中央値の半分の値、これを「貧困線」というのですが、その貧困線に届かない人の割合を指します。
貧困率を下げることの意味
この貧困率を引き下げることが今後の対策としては重要になってきます。
それは、貧困と言われる層の割合が大きければ、教育や文化的活動に使うお金も少なくなりますし、そのことは日本の文化的水準を押し下げることに繋がってしまうからです。
このことは、日本全体だけでなく、地域や自治体単位でも言えることです。つまり、貧困率を低く抑えることは、その地域全体の発展にも大きく影響します。そのための政策にどう取り組むかで、地域の将来が変わってくるとも言えるのです。
福祉だけではない貧困対策
貧困対策は、福祉の分野だと思われている方が多いと思います。確かに福祉の部分は、最終的な支援であったり、人的フォローであったりします。これを風邪のような病気で例えるならば、「医者にかからなければならない患者さん」の段階です。
それ以前に「風邪気味だったら無理をせず体を休める」「病気にかからないよう免疫力を高める生活をする」といった段階があります。貧困においても同じで、貧困になりそうな方を早めにフォローし、経済的な安定が得られるような仕事を探す、あるいは収入が安定的に得られるように資格取得を支援するなど、福祉以外の分野も関わってくるのです。
社会全体で取り組むべき課題
行政が上ばかり見て仕事をしていては、市民から離れていくでしょう。
目を向けるべきは、経済的にも厳しい人々をどのように支援し、安定した生活が送れるようにするのか。豊かになったと実感できる人々をどう増やしていくのか、という点です。
所得が増えれば支出も増え、必然的に消費も拡大し、流通量も増えます。これは社会全体を良い方向に向かわせる力となります。したがって、貧困対策は社会全体で取り組むべき課題と言えるのです。
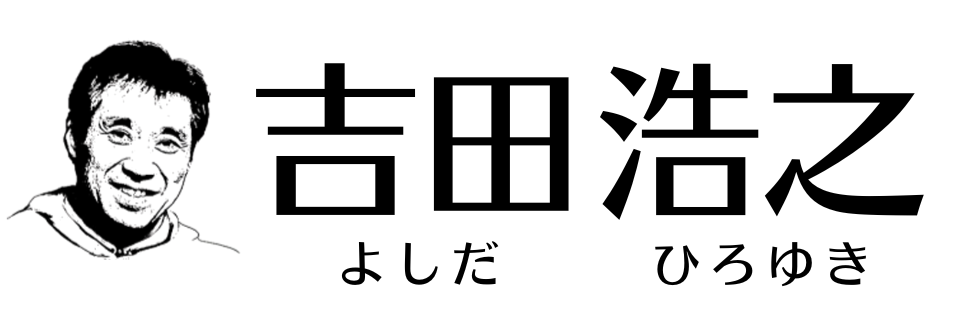









コメント