テレビCMに映る「人の流れ」
珍しくテレビを眺めていました。最近は、番組の内容よりコマーシャルの時間の方が長いくらいではないかと思ってしまうほど、このCМが長いのですが、そのほとんどが日常生活の中で使われる食品であったり洗剤であったりするわけです。そして、その中心は、商品ではあるのですが、人々の生活感ある動きなのです。人と人との交わり、人流がCМの基本と言えます。
都市開発の専門家の言葉で次のようなフレーズを聞いたことがあります。「開発が成功した時のイメージは、朝日が降り注ぐ中でお父さんと子どもたちが『行ってきます!』と元気よく出かけていく姿が1つ。もう一つは開発が失敗した時のイメージで、誰も住まないその街の中で初冬の空っ風に枯葉が舞い、日が暮れていくその両方の数を頭に描け」というものです。きわめて抽象的ながらも誰でも理解できるそのシーンの意味することは、その主役は建物ではなく、居住する人間なのです。テレビCМで伝えようとしていることもこの言葉と同じだなと思うのです。
ウーブン・シティと未来都市への視点
そうした中、トヨタ自動車の実証都市「ウーブン・シティ」が始動しました。都市の中身を詳しく知らないため、どんな街なのかわかりませんが、次世代モビリティー社会の実現を目指すとしています。具体的な街の様子はわからないのですが、自動運転、自動配達といったモビリティ中心の実証実験と理解しています。
ウーブン・シティは先進的近未来都市像ということなのでしょう。ただ、こうしたビルとアスファルト舗装された道だけの都市に住んでみるかと聞かれれば、施設見学だけにしてくださいと言ってしまう自分がいます。やはり、緑あふれる自然が身近にあり、鳥のさえずりや虫の音が聞こえる伊那市の環境の方が落ち着くし、元気が出ます。
街に必要なのは「人のエネルギー」
世界から人が集まる東京よりもインドのニューデリーやインドネシアのジャカルタの方が雑然としてお世辞にも綺麗とは言えない街の方が底知れないパワーを感じるのは何故でしょう。
数十年前の伊那市の通り町が人であふれかえり、買い物客でごった返していた時の方が、今よりもエネルギーを感じていました。
便利になることと街が発展していくこととはイコールではありません。人を引き寄せるパワーはやはり人であり、人流なのではないでしょうか。明るい笑い声や元気な挨拶の聞こえる街か、人気のない枯葉舞う寒々しい街か、それはいかに街中に人が集められるかによるのではないでしょうか。そういった意味で、トヨタ自動車のウーブン・シティも雑然としながらもエネルギッシュな海外の発展途上国とを比べてみることで見えてくるものがあるかもしれません。
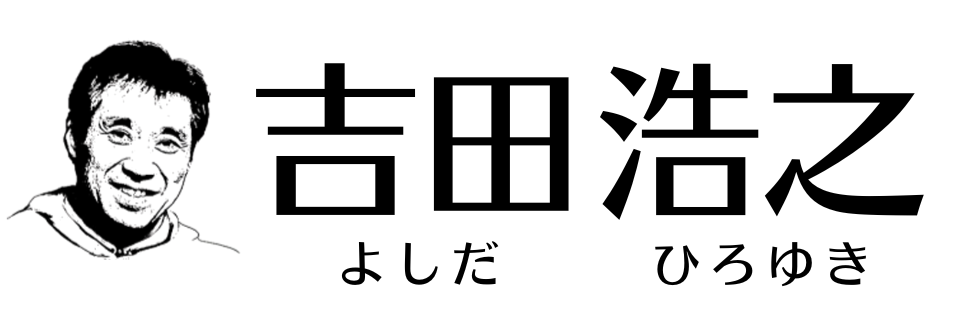







コメント