「消滅可能性自治体」という警鐘の意味
「人口戦略会議」が消滅可能性自治体として全国の市町村を取り上げましたが、これは20~30代の女性の減少率をベースに算出したもののようです。確かに各自治体に警鐘を鳴らすという意図はあるのでしょうが、実際の意味はあまり大きくないのではないかと思います。
そもそも今から25年後の自治体がどうなっているかを正確に予測することは難しいのです。
都市の人口動態を左右する要因
たとえば、現在人口が増え、若い女性が流入している都市として、つくばみらい市や流山市、関西なら栗東市などが挙げられます。つくばみらい市や流山市は、つくばエクスプレスの影響が大きいでしょう。
現在の各都市の状況も、交通網や大きな企業の立地、都市政策、人々の行動によって大きく変化します。今は「成績優秀」とされる自治体であっても、2050年に同じ評価を保てるとは限りません。
また、日本では一度家を建てたりマンションを購入したりすると、転勤など特別な理由がなければ引っ越さない傾向にあります。そのため、若い夫婦が集まる団地も20~30年後には高齢者ばかりの団地になってしまうのです。つまり、今は人口増加が目立つ自治体でも将来の姿は不透明なのです。
本当の意味での人口減少対策とは
世代間の住宅観の違いや、三世代同居から核家族・単身世帯への変化など、暮らし方の多様化を踏まえた人口政策が必要です。若い女性の考え方も多様化しており、女性受けを狙った施策だけでは本質的な人口増対策にはなりません。少子化が止まらない中で、受け狙いの施策に頼るだけでは限界があります。
一方で、首都圏や関西圏の大都市は、単一の自治体ではなく、周辺自治体を巻き込んで肥大化することで都市全体の吸引力を高めてきました。人は人の集まる場所に集まります。一自治体単位で人口増減を論じるのではなく、広域的な視点で人口減少対策を考えていく必要があるのではないでしょうか。
大きな天体ほど引力が強いように、人の動きにも同じことが言えるのかもしれません。
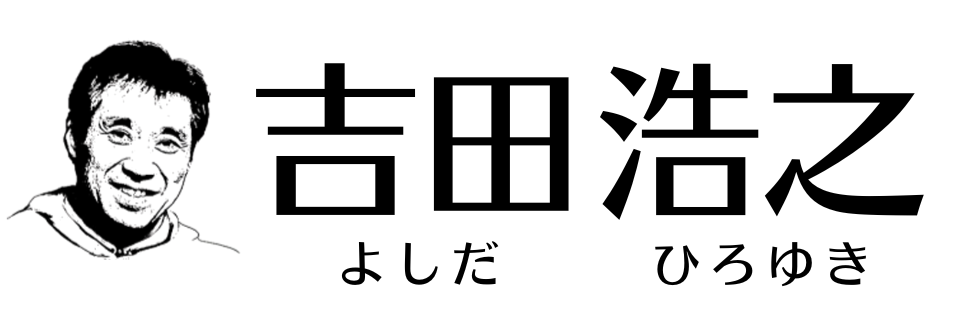









コメント