後継者未定の農地が5割を超える現実
9日に、農水省は、10年後の後継者が決まっていない農地が、17都府県で5割を超えたとの調査結果を公表しました。後継未定の農地が5割を超えているのは、西日本に多く、東京、大阪は8割、沖縄、徳島、香川では7割を超えたとのことでした。ちなみに長野県は35%ほどとのことでした。
ただ、これも現時点の数字であって、私の肌感覚では、伊那市当たりでも5割に近いのではないかと見ています。
人手不足と農地集約の限界
個人で農業をしていて、なおかつ後継者がいそうな農家は数えるほどであり、多くは農地を持っているものの大規模農家や農業法人に耕作を委託しているからで、個人にしても農業法人にしても、人手不足から、今が目一杯の受託状況であり、新たな受け入れは厳しいと言える状況にあります。
そうした中で、農地を集約し大区画化することで効率的に耕作ができるようになれば、後継未定とならず、法人なりが後継者となるであろうということを想定しているのでしょう。
しかし、それでも後継は難しい状況にあります。とにかく、大規模な個人農家でも農業法人でも作業員の確保ができないのです。そのため、集約化してもそこを耕作する者がいないという状況に変わりはなく、たとえ効率的な耕作地となったとしても、耕作放棄地になってしまうことが懸念されるのです。
特に、中山間地の多い伊那市では、大区画化が進みにくい状況にあり、たとえ大区画化を進めても農地の半分近くが土手になってしまい、急斜面の広い土手の草刈りは誰もが敬遠するところであり、受託したがらない農地の一つになってしまう恐れがあるのです。
農業の未来を守るために
農業をしても生活できない、やっていけない。農業は体への負担も大きく、きついわりに収入も少ない。となれば、年金生活者の趣味くらいにしか農業は、その意味を持たなくなってしまうのかもしれません。農地を守り、維持するためには、農地を耕作することは、サラリーマンよりも高収入であることが求められるでしょう。
生活の安定を求めても安心して就業できるように、農業の在り方を見直さなければ、10年後には、農地は荒廃し、食糧不足に陥ってしまいかねないのです。
今、抜本的な解決に取り組まなければならない時期に来ているのです。ひょっとしたら遅すぎるのかもしれません。
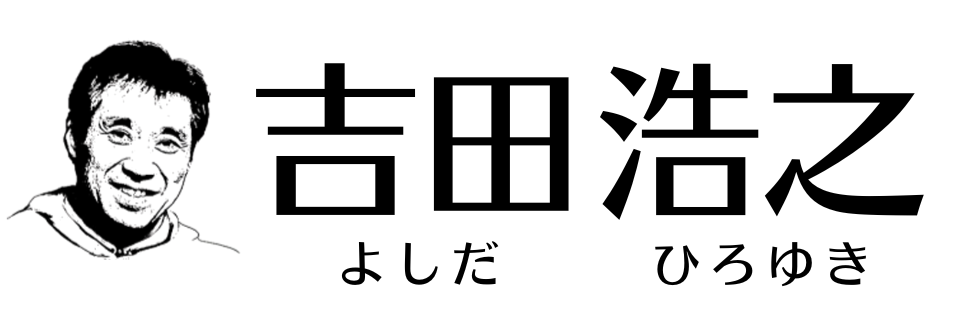









コメント