お盆の時期と人々の過ごし方
今日までがお盆でした。13日からの4日間は、日本人にとって正月と並び思い入れのある時期と言えます。そのため、どこの道路や鉄道も渋滞や乗車率100%超えなどとニュースになるわけです。
ところが最近は、お盆に帰省しない人が増えてきているというニュースもあります。人混みも激しく、移動自体も割高なこの時期を避け、もっと落ち着いた時期に実家へ帰り、ゆっくり家族と話したいという人が増えているのです。かつてのように「一斉に休暇を取らなければ休めない」という状況も減り、休暇を取りやすくなったことも要因の一つでしょう。
各地で行われるお盆行事
お盆というのは、各地でさまざまな行事が行われます。花火大会や盆踊りといった昔ながらの催しから、この時期にできるだけ多くの人を集めようというイベントまで多様です。賑やかなイベントだけでなく、地域を見つめ直したり、魅力を再発見するような企画も増えており、特に地域限定のイベントにはそうした傾向が見られます。
一方で、昔ながらの行事を大切にしていこうという取り組みも続いています。しかし、踊り手や神事の担い手が少なくなり、開催自体が危ぶまれるケースも少なくありません。多くの運営組織にとって、人手不足は深刻な悩みになっているのです。
行事存続のカギは参加意識
開催する側より、見物する側に回る方が楽であることは確かです。そのため「自分から何とかやってみよう」と手を挙げる人がどれほどいるのかが、行事やイベントの存続を左右する大きなカギとなっています。
お盆に帰省する人が減れば、主催者側の意気込みも冷め、積極的な参加者も減少するでしょう。お盆の人混みを避けることは賢明な選択ではありますが、それが進むことで、さまざまな伝統行事が消えてしまうのではないかと危惧せざるを得ません。
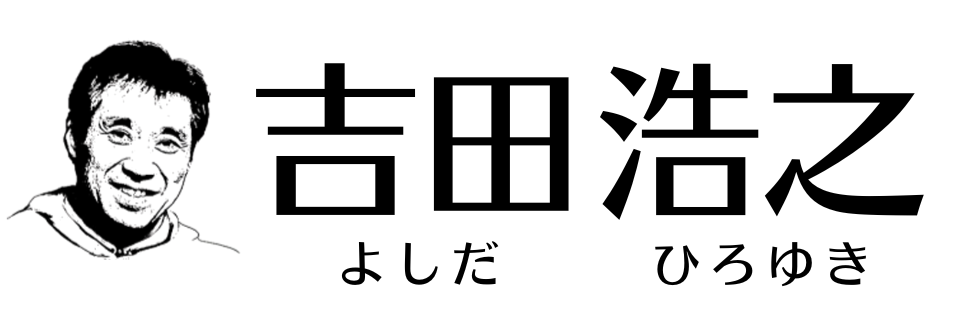









コメント