フィンランド視察報告会が開催されました
先日、フィンランド視察報告会がありました。これは、5月に市長や正副議長をはじめ、市職員、公募の市民など総勢18名によるフィンランドの教育と産業の視察でした。それぞれ得るものがあったのでしょう。思いを熱く語ってくれたので、2時間半にわたる大報告会でした。
その中で、気になる点を3点書かせていただきます。
1. 自己責任という価値観の違い
1点目は、「自己責任」という言葉です。学校においてもどこにおいても、自己責任だから自分の行動は自分で責任を持ちなさいという社会がフィンランドということです。確かに、500万人程度の人口で日本と同じくらいの国土で人を管理するというのは難しいでしょう。だから自己責任というのでしょうが、日本はそれが通用しない社会です。
判例で、生徒が部活中に熱中症で倒れ亡くなるという事件で、学校側は適時休憩を取らせ、水分補給もしていたため落ち度はないと主張しましたが、給水した水分量まで把握していなかったということで学校側の過失が認められました。これが今の日本社会です。そこで、「自己責任だから」と言うことは許されないのです。亡くなったのは高校生です。小学生ではないのです。「自己責任」は素晴らしいから日本でも、とは言えないのです。
2. 「なから」の価値と日本のモノづくり
2点目は、「なから」がいいという報告です。「なから」というのは方言ですが、適当とかいいかげんという意味です。木工製品を端材で作るのだから「なから」のもので緩く作るのがいい。日本はきっちりしすぎているということでした。
これは、日本のモノづくりの原点を否定してしまうような報告ではないかと残念に思いました。端材でも、日本では材木を大切に使い、割りばしという文化を作りました。フィンランドの木材を使った文化は多様であり、日本は無駄が多いというような報告は、もう少し日本の文化や技術について学んでほしいものと感じたのです。
3. 木材を使った繊維化の取り組みへの疑問
3点目は、木材を使った繊維を伊那市でも製作し、それを織物として活用していきたいという市長の報告です。木材のセルロースを使い、それを繊維としてタオルやジャケットなどとして織り込んでいくというものです。
これは何を求めているのかわかりませんでした。木材の多様性を研究するうえでは一つのアプローチですが、その材料の調達や需要の可能性があるのか全く不透明な状態で、行政が木材の繊維化に取り組むというのは、行政として方向が違うのではないでしょうか。その繊維に触っていないので、麻に近いのか、綿に近いのか、あるいは化学繊維のようなものなのか、いずれにしても需要の創出まで相当に時間がかかると思いますし、そもそも木材が不足しているという現状において繊維を作るという目的がよくわからないのです。
フィンランドの良さと同時に必要な冷静な視点
すべての報告者がフィンランドの良さを強調していたのですが、完璧な国はないのであって、マイナスという点も報告にあってほしかったというのが報告会の感想です。 今日はこれまで。
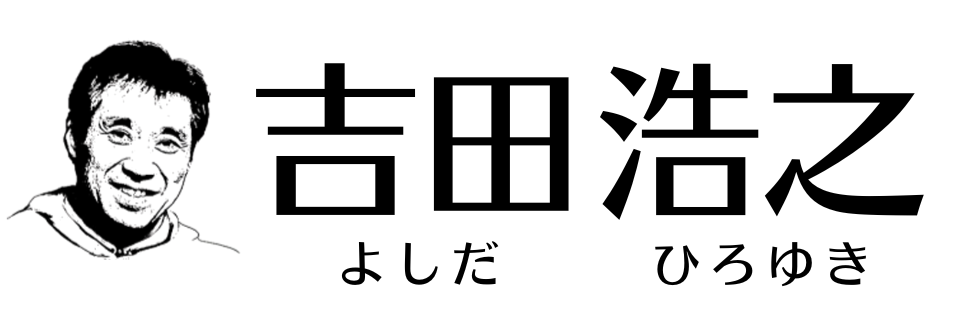









コメント